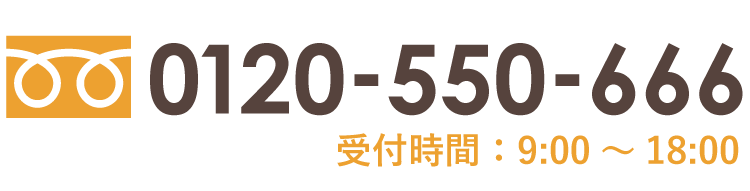
資料請求・見学は無料です。



| 施設の種類 | 施設数 | 定員数 | ||
|---|---|---|---|---|
|
民間 運営 |
有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム | 3,308 | 203,914千人 |
| 住宅型有料老人ホーム | 5,100 | 143,466千人 | ||
| 健康型有料老人ホーム | 16 | 611千人 | ||
|
その他の 施設 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 7,003棟 | 230,311戸 | |
| グループホーム | 12,597 | 184,500人 | ||
| シルバーハウジング | 23,298戸 | |||
| 施設の種類 | 施設数 | 定員数 | ||
|---|---|---|---|---|
|
公的 施設 |
介護保険施設 | 介護老人福祉施設 | 7,705 | 530,280人 |
| 介護老人保健施設 | 4,241 | 370,366人 | ||
| 介護療養型医療施設 | 1,324 | 59,106人 | ||
| 福祉施設 | ケアハウス | 2,007 | 80,387 | |
| 養護老人ホーム | 954 | 64,091 | ||
介護付有料老人ホーム
・幅広い層に対する受け入れ体制が整っている
施設によりますが、自立の方から要介護5の寝たきりの方まで、幅広く受け入れています。
インシュリン注射、胃ろう、吸引などの医療依存度の高い方を受け入れたり、数はまだ少ないですが、呼吸器をつけた方を受け入れたりするような、かなり看護体制が充実した施設もあります。
・レクリエーションの種類が多い
・24時間介護サービスを受けられる
・介護費用が一定である
・入居一時金や月額利用料などの額によって、立地、設備、リハビリテーションの回数、居室の広さなど、ある程度自由に選ぶことができる
介護付有料老人ホーム
・入居一時金が必要な施設もあり、月額利用料も比較的高額である
・介護サービスは、外部の事業所と契約できない
・訪問診療も、契約のクリニックが決まっているので、入居するとそれまでのかかりつけ医に継続して往診してもらえない
難病や難しい病気などを抱えているケースで、今までと同じ病院やクリニックに通院したい、往診してほしいという場合は、施設と相談が必要になります。
住宅型有料老人ホーム
・必要な介護サービスを選択できる
・幅広い層に対する受け入れ体制が整っている
・レクリエーションの種類が多い
・24時間介護サービスを受けられる
・入居一時金や月額利用料などの額によって、立地、設備、リハビリテーションの回数、居室の広さなど、ある程度自由に選ぶことができる
住宅型有料老人ホーム
・入居一時金が必要な施設も多く、月額利用料も比較的高額
・施設によっては、訪問診療や介護サービスは契約している医療法人や自社の事業所に決まっている場合がある
・必要な介護の内容により、利用料金が変わる
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・敷金などが必要だが、入居一時金はなく、入居時の費用が比較的安い
・必要な介護サービスを自由に選択できる
・買い物に行くなど、自宅と同じように自由に生活できる
・自宅近くであれば、訪問診療や訪問看護、介護サービスも継続して利用できる
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
・介護が必要になった場合、要介護度が高くなると負担が高額になる場合がある
・要介護度が高かったり、認知症が進んでいたりすると入居を断られる場合がある
・自立している方が多く、介護スタッフがあまり介入しないので、住人に気の合わない方がいるとストレスになる場合がある
グループホーム
・比較的低価格で入居できる
・認知症のための機能訓練やレクリエーションを考えて行っている
・少人数で家庭的な雰囲気の中でケアを受けられる
グループホーム
・地域密着型サービスなので、同じ地域に住民票がないと入居できない
・医療依存度が高いと入居できない。病気で入院した場合、退院後の容体によっては戻れない場合がある
・感染症や他者への暴力など、共同生活に支障をきたすことがあると入居できない
特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)
・入居一時金はなく、収入に応じて費用の減免もあり、月額利用料が低額
・終身で利用が可能
特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)
・特に都心は入居待ちの人数が多く、状況によっては数ヵ月から1年以上待つ場合もある
・原則として、入居資格は要介護3以上に限られている
・費用を安く抑えるため、立地は交通の便が悪いところが多い
・医療依存度が高い方は入居できない施設が多い
・新しいユニット型の個室タイプもあるが、従来型の相部屋のタイプはプライバシーを確保できないことも多い
介護老人保健施設(老健)
・入居一時金はなく、収入に応じて費用の減免もあり、月額利用料が比較的低額
・医療・看護体制が整っていて、理学療法士や作業療法士など専門職がリハビリテーションを行う
介護老人保健施設(老健)
・入所期間は基本的に3ヵ月、長くても1年程度で退所しなければならない
・季節行事を開催する施設もあるが、レクリエーションはほとんどない
・居室は基本的に相部屋
介護療養型医療施設
・入居一時金はなく、月額利用料が比較的低額
・医療・看護体制が整っているので、気管切開、IVH(中心静脈栄養)、24時間の痰吸引など医療依存度の高い方を受け入れている
介護療養型医療施設
・入所期限の規定はないものの、将来は廃止になることが決まっているので、将来的にその施設がどうなるのかを事前に確認する必要がある
・医療ケアが中心で相部屋がほとんど
・季節行事やレクリエーション活動はほとんどない
軽費老人ホームやケアハウス
・入居一時金はなく、収入に応じて月額利用料が決まるので、低額で入居できる
・ケアハウス(軽費老人ホームC型)は介護サービスが受けられるので、介護度が高くなっても住み続けられる
軽費老人ホームやケアハウス
・資産や所得が少ない方が優先的に入居できるので、収入によっては入居できない
・軽費老人ホームは、入居待ちが多い
・軽費老人ホームA型・B型は自立の方が対象なので、介護度が上がった場合退去しなければならない
・ケアハウスは、入居一時金や月額利用料が高額な施設がある
シニア向け分譲マンション
・自分の資産になる
・自立した高齢者が住みやすいようにバリアフリー化され、食事も工夫されている施設が多い
・レクリエーションやイベントが充実している施設が多い
・施設のスタッフや看護師が24時間常駐している施設では、安心して生活できる
シニア向け分譲マンション
・入居一時金や月額利用料が高額
・将来的に介護度が上がったり認知症が重くなったりすると住み続けられない場合がある

自立・要支援1~2の方が入居できる施設
サービス付き高齢者向け住宅や軽費老人ホームA型・B型、シニア向け分譲マンション、シルバーハウジングは、おおむね60歳以上の方であれば入居が可能です。
シルバーハウジングは自治体により入居資格が65歳以上のところもあるようです。
これらの施設は、介護サービスについては在宅の場合と同じですので、要支援の認定を受けて介護予防サービスを受けたいときは、地域の包括支援センターやケアマネジャーに相談して、近くの介護支援事業所と契約をします。
また、有料老人ホームには「自立」の人から入居できる施設と、要介護認定を受けていないと入居できない施設とがあります。

要介護1~2の方が入居できる施設
現在、要介護度1~2の方は施設の選択肢がもっとも多いでしょう。
特別養護老人ホーム以外であればどの施設もほぼ入居可能です。ですから、要介護度だけでなく医療依存度や認知症の有無も考慮して、以下を参考に選ぶとよいでしょう。
グループホームの入居資格は、認知症の診断を受けた要支援2以上の方です。しかし、共同生活をするので、他者に暴力をふるうなど迷惑行為があったり感染症にかかっていたりする方は入居が難しくなります。
軽費老人ホームはC型であれば入居可能ですが、A型とB型は状態によっては入居が難しいかもしれません。
サービス付き高齢者向け住宅は、入居は受け入れられますが、介護サービスは外部の事業者と契約する必要がありますし、日常の生活援助や夜間の介護については別途料金がかかりますので、事前の確認が必要です。
なお、それぞれの施設の特徴は別項「施設の種類と特徴」を参考にしてください。
要介護3~5の方が入居できる施設
軽費老人ホームA型、B型以外の施設に入居できます。
とはいえ、要介護5になるとほとんど寝たきりの状態のため、施設側も介助にはそれなりの人員が必要です。ですから、要介護度が重い方は、その施設の状況によっては受け入れられないことがあるかもしれません。
また、要介護度が上がると医療依存度が高い方も増えます。経管栄養や夜間の痰の吸引などが必要な場合は、介護療養型医療施設や介護老人保健施設でないと、受け入れが難しくなります。
ただし、この頃は有料老人ホームでも医療依存度の高い方を受け入れている施設がありますので、具体的に実施してもらいたい医療処置を説明し、対応可能かどうかを確認しておくことは大切なポイントです。
